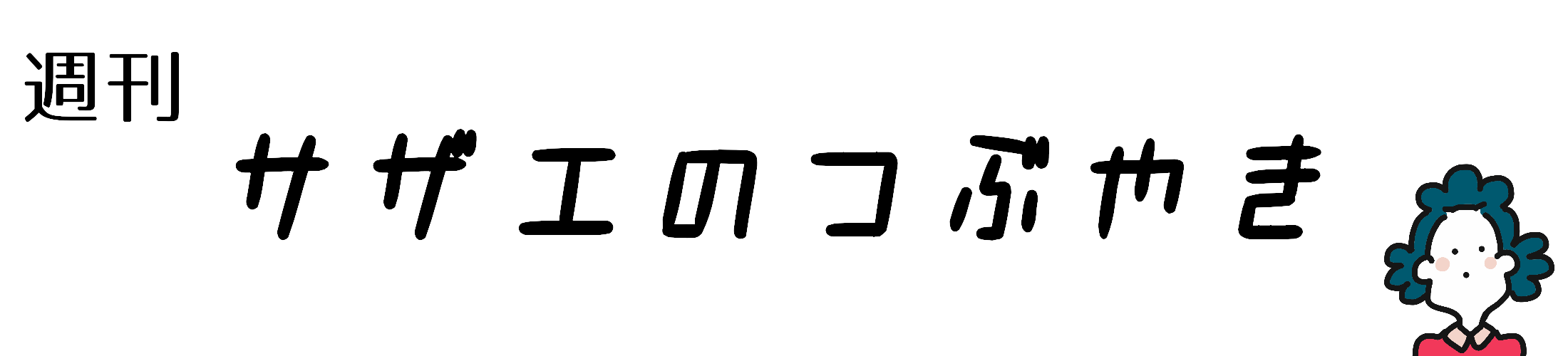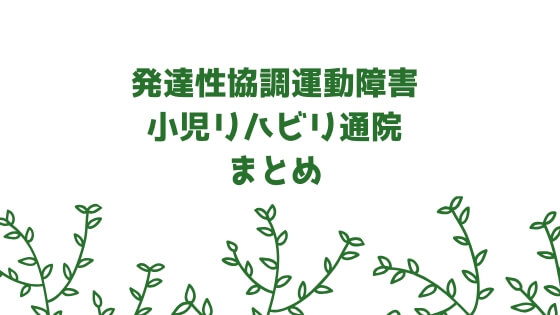発達性協調運動障害って、あまり聞きなれない言葉ですよね。
わたしも、この「発達性協調運動障害」って症状名は、たまたまネットで見かけて知りました。
>>発達性協調運動障害とは?|長男が下校途中に転倒してケガをした理由
長男はADHDの傾向があると言われています。
いわゆるグレー判定を受けています。
発達性協調運動障害は、ADHDの子が併発する率が多い障害の一つと言われています。
へやすぽアシスト|運動苦手&発達が気になる子ども向けのオンライン個別運動教室の無料体験予約
発達性協調運動障害とは?特徴は?

別名を不器用症候群とも言います。
この方が、わかりやすいと思いますが、発達性協調運動障害とは、年相応の協調運動が何かしらの障害でうまく行うことができないという状態を言います。
一昔前なら、もの凄い運動音痴で片付けられてきたことかもしれません。
専門家による、詳しい解説はこちらのサイトがわかりやすいかと思います。
3歳児健診でグレー判定
我が家の長男は、区の保健センターの3歳児検診で発達面でグレー判定を受けました。
グレー判定ということでしたが、療育に通う程でもなく、幼稚園での集団生活の様子をみていきましょうとの判断で、過ごしてきました。(市の療育機関が既に満杯で空きがすぐにないということも理由の一つ)
発達障害がグレー判定ということで、少し不安があり小学校入学前には小児精神科の専門の先生を紹介していただき、数か月に一度のペースでアドバイスをいただきに受診することにしました。
アドバイスのお陰で、子どもにとって大事なことは「心の安定」だということを教えていただき、理解しているようでわかってなかった我が子の様々な行動の理由や、不安定さが少しづつ見えてきました。
あれ?ちっとも理解できてなかった!!みたいなことも、結構ありました(;'∀')
AD/HDといっても、千差万別。一人ひとり、程度も違うし行動の仕方も違うと思います。
親が、専門家のアドバイスをいただき、先入観をとっぱらって子どもと向き合う中で、お互いのストレスも無くなり、子どもも親も心が安定していくことができます。
運動面の気になる事、特徴
心が安定してくると、AD/HDの症状的には落ち着いてるように感じましたが、どうしても気になるのが「運動」面でした。
うちの子の気になる特徴としては、
|
とにかく、体幹が弱い!
そして、本人の脳内のイメージと体の動きが合ってない感じ。
気持ちはとっても前向きで、一生懸命なだけに、この不器用さがなんとも不憫でした。
発達性協調運動障害で、運動機能の小児リハビリを受けれるようになるまで

ほんのちょっとづつの、凸凹は「マイペース」という個性でカバーできてきました。
小学校にあがっても、少人数の学校なので、クラスメイトみんなと満遍なく仲良く遊べるし、
授業も、進んで発表できるくらい、楽しく過ごしています。
低学年は、どうにか過ごしてこれました。
が、やはり、少しづつ体育も授業のレベルが上がってきてるし、マット運動や、鉄棒、縄跳び、球技などで、明らかに「できてない」が目立ってきました。
小児リハビリを受けれるクリニックをかかりつけ医に紹介してもらう
どうにか機能訓練が受けれないものかと、かかりつけの小児精神科の先生に相談したところ、市内でリハビリテーションを行っているクリニックを紹介していただきました。
早速、クリニックに電話で問い合わせてみました。
すると、当時(2017年)は初診を受けるまで半年待ちとのことでした。
それでも、リハビリを受けることができるなら、申し込まない理由がありません。
即決で、初診の予約待ちに登録しました。
運よく、キャンセルが発生したとかで、4ヶ月ほどでクリニックの初診の連絡をいただきました。
初診を受けれるのは平日の昼間です。学校がある時間ですが、クリニック側は、当然学校は早退してでも来てくださいとのことでした。
まだ学校には発達性協調運動障害とはカミングアウトしていなかったので、眼科検診と理由づけて、早退しました。
クリニックで、専門医と作業療法士の方に診ていただき、「発達性協調運動障害」との診断。
そこから、リハビリの指示書を書いていただき、保険適用で小児リハビリが開始されました。
いまなら、オンラインでリハビリを受けることができます!
6年前にあったなら、飛びついていたことでしょう。
へやすぽアシスト|運動苦手&発達が気になる子ども向けのオンライン個別運動教室の無料体験予約
発達性協調運動障害で運動機能のリハビリが開始!受診のスケジュールは?

小学生は、10回ワンクールで一旦リハビリは終了します。幼児さんだと、制限もなくリハビリを受けれるようです。たぶん、早く始めた方が、効果も大きいようです。
小学生は予約待ちが溢れているためワンクール終わると、次は初診の予約待ちになります。
10回でどこまで運動機能がアップできるのか、期待いっぱいでのリハビリがスタートしました。
リハビリの予約は1か月に、2回予約が取れればいい方でした。1回60分ほどのリハビリは、子どものモチベーションを上げながら、楽しく安全に行えるように作業療法士さんがマンツーマンで指導してくださいます。
>>発達性協調運動障害の作業療法(リハビリ)は、こんな様子です
最初は面倒くさがっていた長男も、段々とリハビリが楽しみになってきました。
リハビリを受けるにあたって、他の日には普段の様子を専門医に報告、相談をする「保護者診察」という予約再診も受けなければなりません。(これは、保護者のみです)
毎回のリハビリ前や、保護者診察の前には詳しく家での様子や、褒めた事を具体的に問診票に報告しなければならず、簡単に書くと受付でダメ出しされるというのが、一番のストレスでした(笑)

子どもの自己肯定感を増すために、「簡単なお手伝いを課し、それを目一杯褒める」というのが大事ということで、徹底してこの作業を家でしてくださいと指導されます。
1か月に3~4回、市内のクリニックに通うために、幼稚園に通う下2人の送迎の段取りや、スケジュール調整が本当に大変でした。
また、下の子が熱を出したり、一度は高熱で病院で点滴を受けてる時には、母に付添を代わりに来てもらって、点滴中の娘を病院に残し、長男をリハビリに連れて行くこともありました。
キャンセルという選択ができないようなシステムになっていて、1回1回のリハビリに本人の体調も万全にすることも、それはそれはかなりの緊張感でした。
(直前のキャンセルには、キャンセル料が発生します。予約時に予約料という名目で保険外で料金を支払うシステムです。キャンセルした場合、次回の診察時に予約料のみ徴収されてしまいます( ;∀;))
で、ついに10回目。
いよいよ、最後のリハビリの日。
台風が直撃という、悪天候に見舞われました。もちろん、学校も警報が出て休みです。
家から車で小一時間掛かります。
暴風雨の中、車を運転してクリニックに行くにはリスクが高すぎます。
クリニックも理解してくれるかと思いきや、「キャンセル料が発生します。本日で10回目のリハビリが終了ですので、次は初診の予約をお待ちください」とのあっけない終了となりました( ;∀;)
チーン
えーっと。
1月から、約8か月間ほど通ったんですけど、いきなりの終了宣言。
自宅でもできる運動リハビリをレクチャーしてもらう予定が、それも叶わず。
尻切れトンボでなんとも後味の悪い終わり方となりました。
オンラインでリハビリが受けれたなら、どんなによかっただろう・・・。
結局、発達性協調運動障害のリハビリで効果はあったのか?
正直、劇的に変わった!という実感は弱いです。
ただ、本人に自信を持たせて、運動に取り組む姿勢は学べました。声の掛け方など。
作業療法士(OT)さんによる専門的なアドバイスを受けながらのリハビリは、心強く効果も期待が大きかったのですが、1か月に2回ほどのリハビリ運動では、目に見える成果は、、、。
もう少し早い時期から定期的に、長期間取り組めたらと思うと残念で仕方ありません。
公共の機関で、専門的なリハビリをもっと受けれるようになれたらいいのになぁと思います。
自己流でやるには、ケガの心配や継続性の問題がどうしても引っかかります。
ADHDの子は、危険性の認知が弱いので、思ってもみないような大胆な行動をとるときがあります。
オイオイ、ちょっと、それは無理だろうというような動きもやってしまおうとします。神技的に成功しちゃうときもありますが、咄嗟にフォローできる体制が無いと大けがしちゃうこともあると思います。
また、我が家はたまたま調べ尽くして、発達性協調運動障害という障害やリハビリ機関を見つけることができましたが、何も知らず、単なる運動音痴で片付けられ、いじめにつながるような悲しい実態も少なくはないと思います。本人も自信がなくなり、いろんな面で消極的になってしまうかもしれません。
発達性協調運動障害という障害が正しく広く認知され、本人たちが目一杯努力しているということを理解してもらえたら、もっともっと楽しく学校に通ったり、得意なことを伸ばしたりできる子どもたちが増えると思います。
診断を受けてなくても、試せるオンラインでのリハビリ無料体験があります!
気になる方は、ぜひ一度申し込んでみては?